お客様の声
お客様よりいただいたご意見・ご感想の一部をご紹介いたします。
住まいリレーコラム
2024.11.12

50代60代ともなると子どもが独立して使わない部屋が増え、部屋数の少ない家への住み替えを考える人もいるのではないでしょうか。
もしくは、現在は戸建てに住んでいるものの、老後のことを考え、交通の利便性のいい場所にマンションの購入を考える人もいるでしょう。
そこで今回は50代60代で住み替えを考えるにあたって、どのような選択肢があるのか、メリットやデメリットも合わせて解説します。
老後の住まいを考える際には、どのような生活スタイルを送りたいか、ということが重要なポイントになります。病院に通う頻度が高くなることが予想されるため、できるだけ交通手段のよい場所に住みたいと思う人もいれば、老後は郊外の静かな場所でゆっくりと過ごしたいと考える人もいるでしょう。住まいの選択肢はさまざまですが、それぞれの特徴およびメリット・デメリットを十分に把握した上で決めることが大切です。
マンションは戸建てに比べて防犯性が高い点が特徴です。
現在は、オートロックの物件が大半を占め、さらにエントランスには防犯カメラが設置されるなど、防犯に対する設備が整っています。
また、共有部分の管理や清掃については管理会社に任せられる点もメリットでしょう。
戸建てであれば、玄関まわりや庭の掃除は自分でする必要がありますが、マンションならその必要がありません。
50代~60代の住み替えともなると、住まいの中での移動も考慮しなければなりません。
戸建てでは平屋でない限り上下の動線は避けられませんが、上下の移動がないマンションは、戸建てに比べると移動の負担が少なく、階段での転倒などの事故を抑えられます。
また、バリアフリー設計にすることで、車椅子での移動も楽です。
マンションへの住み替えにおけるデメリットも確認しておきましょう。
まず注意したいのは、騒音です。
マンションでは、集合住宅ならではの左右上下の騒音に悩まされる可能性があります。
家同士が密接しているため、戸建てでは気にならなかった他人の生活音が気になる方もいるでしょう。
特に、最近はペット可としているマンションも多くありますが、ペットの鳴き声や歩く音は意外と響くものです。
ペットを飼うほうも隣近所に気を遣いながら生活することにストレスを感じるかもしれません。
また、 車を所有している場合は、駐車場の空きや駐車場代を確認しておく必要があります。
住み替えた後に後悔することがないよう、マンションに住み替える際にはペットを飼ってもいいのか、飼うとしたらどのくらいの大きさまでなら大丈夫なのか、また駐車場の契約方法や停められる車の大きさなどマンションの管理規約を十分に確認しておきましょう。
戸建てのメリットは隣の家との距離が保たれるため、マンションのような騒音問題を気にする必要がない点です。
マンションのようにペット不可などの規制もないため、飼いたいペットを自由に飼える点も魅力と言えるでしょう。
また、敷地内に駐車場があれば、駐車場代を気にする必要もありませんし、車のサイズも自由に選べます。
庭に好きな花や木を植えるなど自由に使える空間が広くとれるため、制約に縛られたくないと思う人には戸建てが向いています。
さらに、戸建てはもし住まなくなったとしても土地を活用できます。
これはマンションにはないメリットです。
需要があれば更地にして駐車場にしてもいいでしょう。
また、建て替えて子どもたちが住むといった選択肢もあります。
戸建てに住み替えるデメリットは、防犯対策が必要な点です。
オートロックのマンションと比べると窓や裏口などから侵入される危険性が高く、ちょっとした外出でも窓を全部締める必要があるほか、できればカーテンも閉めて出掛ける必要があるでしょう。
また、2階建てや3階建ての家であれば階段での移動が必要になり、高齢になるにつれ上下の移動が苦痛に感じる可能性もあります。
階段は、つまずいたり滑ったりしてけがをする原因にもなりかねません。
そのため、50代60代から戸建てへの住み替えを考えるなら、平屋がおすすめです。
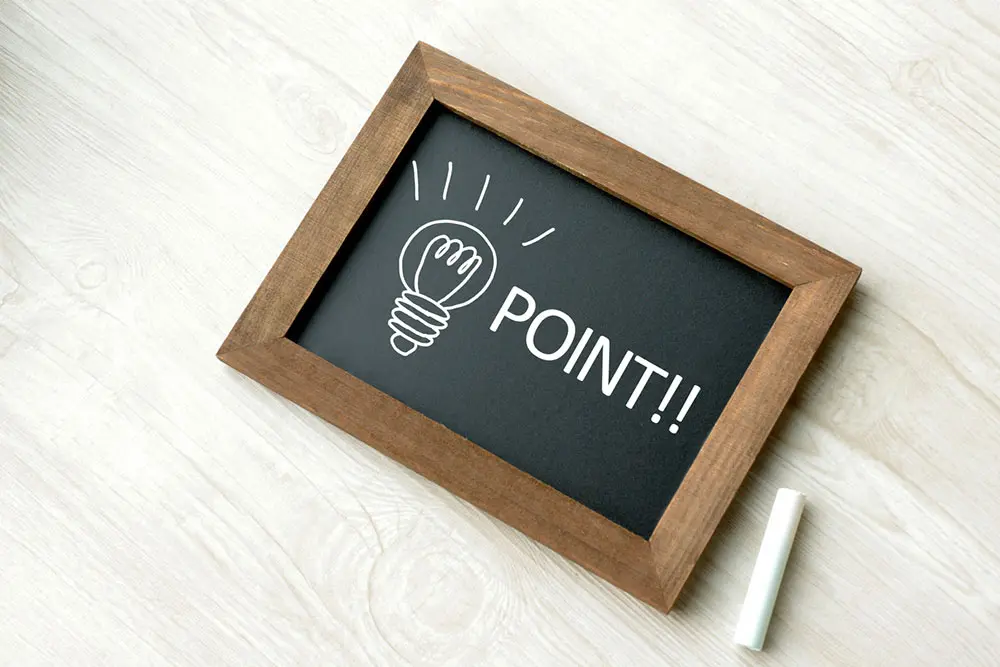
どのタイミングで住み替えを考えるべきなのか、悩まれる方も多いでしょう。
老後の住み替えを考え始めるタイミングは人によって異なります。
子どもの独立を理由に住み替えを考える人もいれば、退職が近くなったタイミングで住み替えを考える人もいます。
ここでは住み替えを考えるにあたって代表的なタイミングを紹介しますので、住み替えのタイミングを考える際の参考にしてください。
一般的に老後の住み替えは、定年を控えた50代から考え始める人が多いようです。
時間や場所から開放される定年退職は人生の大きな区切りとなり、今までとは違った生活にチャレンジできるタイミングです。
「田舎でのんびり暮らす」「2拠点生活に挑戦する」「子どもの家族の近くに住む」など、現在はさまざまな選択肢があります。
現状と今後の要望を考慮しながら、適切なタイミングと住み替え先を検討しましょう。
住んでいる家が劣化してきたため、修繕費用が必要になったタイミングで住み替えを考える人もいます。
築年数によっては修繕費用が高額になるため、その時の状況によっては住み替えた方がいいと考えるでしょう。
一般的にリフォームや建て替えには高額な費用がかかります。
それらの資金を準備しているなら、いっそのこと新しい家に住み替えた方がその後の維持管理費の心配も少なくなるでしょう。
また、住み替えの際にはその後のライフスタイルに合った家を選択できるため、今後のライフプランを話し合いながら住み替える家を探すのもおすすめです。
その時には戸建てとマンションのどちらがいいかなど詳細な部分まで比較して決めるようにしましょう。

老後の住み替え先を選ぶ際には、「どのような場所に住むのか」や「どのような建物に住むのか」、さらには「住み替え先の物件の資産価値」など、考えるポイントもさまざまです。
全ての希望を叶える住み替え先を選ぶことは難しいため、どこまでなら妥協できるのか、もしくはここだけは譲れないといった条件を明確にし、優先順位をつけることが重要となります。
ここでは、住み替え先を選ぶ際のチェックポイントについて詳しく解説していきます。
どのような場所に住むのかは、老後の生活を送るうえで非常に大切なポイントです。
今後、車を手放すことを考えているなら、バス停や駅などの近くはもちろん、バスや電車の路線や一日に走っている本数も考慮しておきましょう。
また、食品や日用品を購入するスーパーマーケットや、メインに使っている金融機関が近くにある場所を選ぶことも大切です。
さらに、老後は病院にかかる頻度が高くなることが予想されるため、かかりつけ医になりそうな通いやすい病院が近くにあるかどうかも考えておきましょう。
あわせて、何かあった際に頼れる家族や親族ができるだけ近くにいる場所を選ぶことも大切です。
そして、普段から家族や親族と連絡を取り合っておくなど、日頃の情報を共有しておくように心がけておきましょう。
高齢者には少しの段差も危険といわれていますので、段差がないバリアフリー設計は見逃せないポイントです。
また、防犯カメラを設置するなど、セキュリティ対策も怠らないようにしましょう。
マンションの場合、オートロックなどセキュリティ対策を行っている物件が多いですが、戸建ての場合は自分で行う必要があります。
また、間取りを考えることも重要なポイントです。
使わない部屋があると、必然的に物置化してしまいます。
不要なものはできるだけ処分することを考えるとともに、生活する上で必要最小限の間取りを確保することを考えましょう。
そして、将来身体の動きが不自由になる可能性も考え、寝室とトイレを近くするなどといった生活動線も考慮しておくと安心です。
将来、再度住み替える必要性が生じたり、子供が相続した時のことを考え、物件の資産価値をポイントに住み替え先を選ぶという考え方もあります。
立地条件や間取り、築年数によっては高値で売却できる可能性がありますし、今後の周辺環境の変化によっては、購入時よりも資産価値が上がる可能性もあります。
資産価値が高いのであれば、売却だけでなく、自分が退去した後に賃貸に出すことで、賃料収入を得るという選択肢もあります。
仮に新しく購入する際は、資産価値の高い住宅に住み替えることが今後の資産形成に繋がったり、相続が発生した場合、対象財産である不動産が賃貸用であれば評価額がさらに下がるため、相続税対策にもなることを覚えておきましょう。
シニアの住み替えを成功させる一番のポイントは、「いかに早めに取り組むか」です。
子どもが独立したタイミングで自分の年齢を考慮しながら、いつまでこの家に住み続けることができるかを考えましょう。
その際には、リタイア時点での貯蓄額、そして年金収入がどのくらいあるのかを把握し、老後の生活を送るにあたって収支がマイナスにならないよう、余裕を持って資金計画を立てることが大切です。
これまで子どもと同居しており、老後は夫婦2人もしくは単身での生活になるのであれば、これまでよりも部屋数が少なくて済むでしょう。
自分たちが暮らすうえで必要な間取りはどのくらいかを検討し、必要な間取りや広さを見直し再考することも大切です。
また、老後は上下の動線が負担になることが考えられるため、戸建てを考えるなら横の動線で完結する平屋の検討をおすすめします。
あわせてバリアフリー構造としてのスロープや手すりも考慮するとよいでしょう。
特に坂が多い立地の場合、道路から玄関までが階段であるケースが多く、敷地面積によってはスロープの確保が難しい可能性もあります。
そのような状況であれば、思い切って段差に悩むことが少ないマンションを選ぶという手もあります。
資金計画は、住み替えを考え始めた時の状況によって異なります。
持ち家を売却する際の査定額をしっかりと把握し、さらには年金受給額を考慮しながら、新しく購入する物件にどのくらいの費用を充てることができるかを考えましょう。
そのうえで、住み替えた後の住居にかかる費用や、リタイア後にどのような生活をしていきたいかを考えながら、突発的な出費にも対応できるような余裕を持った資金計画を立てることが大切です。
また、住宅ローンが完済していない状況ならば、どのくらいの価格でご自宅が売却できるか現状の資産価値を把握して、売却した費用でローン残債を完済できるかどうかも確認しておきましょう。
中には、将来その家に住みたいと考える子どもが居るかもしれませんので、住み替えを考える際には家族とよく相談してみましょう。
自分だけで考えるのではなく、特に相続に関係する人の意見を聞くことで、今後の選択肢がより具体化する可能性があります。
また、住み替え時には環境や暮らし方も含めてさまざまな変化を伴います。
そのため、自分の不安や悩み、さらには困ったことが起きた際に相談できる存在がいるかどうかを改めて見直してみることも必要です。
相談相手は、子どもや親族だけではありません。
古くから付き合いのある友人やこれまでに住み替えを体験した人の意見も参考にすることで、最終的に後悔しない住み替えを実現することができるでしょう。
60代70代の住み替えには考慮する点がたくさんあります。
そのためにも、なるべく早くから準備に取り掛かることが大切です。
どのような家に住むかといった「住み替え先の選択肢」、さらには住む場所などの「住み替え先を選ぶ際のチェックポイント」、そして資金計画といった「住み替えを成功させるためのポイント」をしっかりと理解したうえで、家族や信頼できる周囲の人ともよく話し合いながら行動に移すようにしましょう。
三菱地所ハウスネットは、50代60代のお客様も多く、住み替えに関するさまざまなご相談を承っております。
何から始めていいか分からないという方も、まずはお気軽にご相談ください。

掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。
三菱地所の住まいリレーでは、他にも住み替えに関するお役立ちコンテンツを豊富に取り揃えております。是非、お気軽にご参照ください。
マンション・土地・一戸建てさっそく無料売却査定を始める
※査定可能エリアのみ表示されます。ご了承ください。
都道府県
市区町村
町名
最適な賃貸プランをご提案しますさっそく無料賃料査定を始める
※査定可能エリアのみ表示されます。ご了承ください。
都道府県
市区町村
町名