お客様の声
お客様よりいただいたご意見・ご感想の一部をご紹介いたします。
住まいリレーコラム
2024.11.07
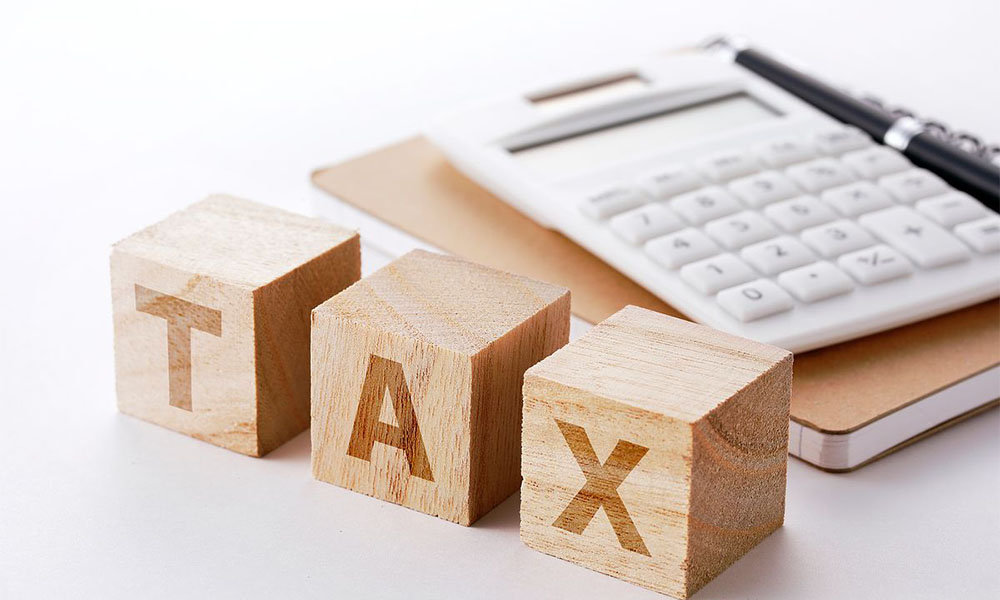
土地の売却を検討しており、どのような税金が発生するのか、いくら税金を納める必要があるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
保有している土地を売却するときには、さまざまな種類の税金が発生します。利益が出ていないときでも発生する税金があれば、利益が出たとき(取得金額よりも売却金額のほうが高いとき)のみ発生する税金もあるため、納税資金について把握しておきましょう。
この記事では、土地を売却したときに発生する税金の種類や相場、節税の方法を解説します。

土地を売却したときには、状況に応じてさまざまな種類の税金が発生します。
納める税金の種類と相場について解説するので、参考にしてみてください。
土地を売却したときの金額が、取得したときの金額よりも高ければ所得税・復興特別所得税が発生します。
不動産を売却したときの利益を「譲渡所得」といい、
たとえば3,000万円で購入した土地が6,000万円で売却でき、売却の際の諸費用(譲渡費用)が500万円の場合、譲渡所得は「6,000万円-(3,000万円+500万円)」で2,500万円です。
譲渡所得に対して以下の税率をかければ、所得税が計算できます。
| 不動産の所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 所有期間が5年以内(短期譲渡所得) | 所得税30%+復興特別所得税0.63%=合計30.63% |
| 所有期間が5年超(長期譲渡所得) | 所得税15%+復興特別所得税0.315%=合計15.315% |
なお、所得税と復興特別所得税を納める時期は、確定申告時(翌年の2月16日~3月15日)です。
住民税も、土地を売却して利益が出た際に発生します。
課税対象となる譲渡所得の計算方法は所得税と同じで、
住民税率は以下のとおりです。
| 不動産の所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 所有期間が5年以内(短期譲渡所得) | 9% |
| 所有期間が5年超(長期譲渡所得) | 5% |
なお、住民税を納める時期は翌年の6月です。
一括払いか4回の分納が可能なので、手元の資産状況に合わせて決めましょう。
所得税と復興特別所得税とは、納付時期が異なる点に注意が必要です。
登録免許税とは、土地の所有権移転登記や抵当権抹消登記を行ったときに発生する税金です。
土地の売主様に関係するのは、抵当権抹消登記を行ったときの登録免許税です。
税額は不動産1個あたり1,000円と決まっており、土地が分筆されている場合は1筆あたり1,000円となります。
抵当権の抹消は司法書士に依頼するのが一般的で、司法書士への手数料を含めて事前に渡します。
なお、所有権移転登記に関する登録免許税は、不動産の買主様が負担するのが一般的です。
税額は「固定資産税評価額×税率」で、税率は令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合は「1,000分の15」です。
以下記事では、抵当権の概要から抹消手続きまでの流れを解説しています。
不動産の抵当権とは?売買の前に知っておきたい基礎知識をやさしく解説
土地の売買契約書を作成したときには、印紙税を納付する必要があります。
収入印紙を購入し、売買契約書に貼付すれば納税は完了するため、税務署へ足を運ぶ必要はありません。
印紙税額は成約金額に応じて以下のように決まっています。
| 契約金額 | 印紙税額(平成26年4月1日から令和9年3月31日までの軽減措置) |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円を超え10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 |
出典:国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
なお、電子契約の場合は印紙税の納付が不要です。
電磁的記録は、印紙税の課税対象となる文書には含まれないためです。
登録免許税と印紙税は、売却したときに利益が出ていなくても納付しなければならない税金です。
売却する前にどの程度の税額が発生するのかを把握しておくと、資金計画を立てやすくなるでしょう。

土地を売却したとき、税額が大きくなりやすいのが所得税と住民税です。
そのため、譲渡所得が発生するときは納付すべき税額を把握し、納税資金を用意する必要があります。
譲渡所得は
です。
売却する前に、土地の取得金額はいくらになるのか、取得時に要した費用はいくらなのかを把握しておきましょう。
また、不動産会社に土地の価格を見積もってもらうことも大切です。
いくらで売却できそうか、目安を知ればどの程度の税金が発生するのか見通しを立てられます。
譲渡所得が発生しない場合、所得税と復興特別所得税、住民税は発生しません。
この場合、登録免許税と印紙税が発生します。
なお、土地の取得費が不明の場合は売却金額の5%を取得費とみなして計算します。
税負担が重くなりやすいため、注意が必要です。

土地を売却したとき、具体的にどの程度の税金が発生するのかをシミュレーションしてみましょう。
シミュレーションの条件は以下のとおりです。
まずは譲渡所得を計算します。
5,000万円-(100万円+3,000万円+100万円)
譲渡所得は1,800万円です。
所得税は
1,800万円×15%=270万円
復興特別所得税は
270万円×2.1%=5万6,700円
です。
また、住民税は
1,800万円×5%=90万円
となります。
登録免許税は1,000円で、売却金額が5,000万円なので印紙税は1万円です。
まとめると、以下のようになります。
| 所得税 | 270万円 |
|---|---|
| 復興特別 所得税 | 5万6,700円 |
| 住民税 | 90万円 |
| 登録免許税 | 1,000円 |
| 印紙税 | 1万円 |
| 合計 | 366万7,700円 |
もし土地の取得費が不明の場合、以下のように算出します。
5,000万円-(100万円+250万円)
譲渡所得は4,650万円です。
所得税は
4,650万円×15%=697万5,000円
復興特別所得税は
697万5,000円×2.0%=14万6,475円
です。
住民税は
4,650万円×5%=232万5,000円
となります。
登録免許税は1,000円で、売却金額が5,000万円なので印紙税は1万円です。
| 所得税 | 697万5,000円 |
|---|---|
| 復興特別 所得税 | 14万6,475円 |
| 住民税 | 232万5,000円 |
| 登録免許税 | 1,000円 |
| 印紙税 | 1万円 |
| 合計 | 945万7,475円 |
このように、取得費が不明だと税額が大きくなりやすいため注意しましょう。
もし土地の取得費がわからない場合、最終的な税額に100万円以上の差が生じることもあります。
実際には、税金の他にも不動産会社への仲介手数料や司法書士への手数料などが発生します。
土地を売却する際には、諸費用を含めて手元に残る金額をシミュレーションしましょう。

土地を売却する際に、税負担を軽減できる特例があります。
特例を活用すれば、場合によっては100万円以上税負担を抑えられる可能性があるため、有効活用しましょう。
以下で、土地の売却時に活用できる節税対策を解説するので、参考にしてみてください。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とは、譲渡所得から3,000万円を差し引ける(控除)できる特例です。
つまり、譲渡所得が3,000万円以下の場合、この特例を活用すれば納付する税額が発生しません。
なお、特例を利用するための条件は以下のとおりです。
※1 住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまること
出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
譲渡所得金額によっては、100万円以上の節税効果を見込める特例です。
ただし、居住用財産に対して適用される特例なので、別荘や投資用のマンションの用途に供していた土地には利用できません。
土地の利用状況によっては適用されないため、注意が必要です。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例とは、所有期間が10年を超える家と土地を売却したとき、譲渡所得に対して以下のように軽減された税率を適用する特例です。
| 課税長期譲渡所得金額 | 所得税と特別復興所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 10.21% | 4% |
| 6,000万円超の部分 | 15.315% | 5% |
なお、本特例を利用する際の要件は以下のとおりです。
※2 住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件すべてに当てはまること
出典:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
例えば、3,000万円の譲渡所得が発生したケースでシミュレーションしてみましょう。
長期譲渡所得に該当する場合、3,000万円に対して所得税・特別復興所得税・住民税をあわせて20.315%が課税されるため、約609万円を納税する必要があります。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例を活用すると、所得税・特別復興所得税・住民税をあわせて14.21%が課税されるため、納税額は約426万円です。
このように、最終的な納税額に100万円以上の差が生まれることもあります。
また、マイホームを売ったときの軽減税率の特例と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は併用できるため、不動産を売却するときには要件に該当するかチェックするとよいでしょう。
取得費や譲渡費用を正確に計上すれば、必要以上に納税する事態を防げます。
譲渡所得を圧縮できれば納める税額を軽減できるため、計上漏れが起きないように注意しましょう。
具体的に、取得費や譲渡費用に計上できる支出は以下のとおりです。
【取得費】
【譲渡費用】
初めて土地を売却する方の場合、どの支出が取得費や譲渡費用に該当するのか、判断できないこともあるでしょう。
適正な納税額を計算するためにも、取得費や譲渡費用に該当するか判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。
前述したシミュレーションで、土地の取得金額が不明だと所得税や住民税が高くなりやすい点を解説しました。
特に注意が必要なのが、相続した土地や先祖代々から受け継がれている土地を売却するケースです。
相続した土地を売却するときの取得金額は、実際に購入した方が取得したときの金額です。
自分で購入した土地ではないため、売買契約書をはじめとした書類が見つからず取得金額がわからない、というケースは往々にしてあり得ます。
この場合でも、売却金額の5%を取得金額として計算しなければなりません。
ただし、取得金額が不明な場合でも、合理的に算出できれば取得金額として認めてもらえる可能性があります。
たとえば、登記簿謄本の抵当権から購入時のローンを推測したり、不動産鑑定士に算出してもらったりする方法があります。
取得金額に関する書類が見つからない場合は、必要に応じて税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談するとよいでしょう。
土地を売却する際には、さまざまな税金が発生するため、事前に資金計画を立てておきましょう。
譲渡所得が発生する場合、所得税や住民税が高額になるケースもあります。
事前に土地の取得費用を把握し、売却金額を見積もってもらったうえで、「どの税金を、いくら程度納付する必要があるのか」を確認しましょう。
三菱地所の住まいリレーは、不動産売買の実績が豊富なプロフェッショナルです。
売主様の税金に関する疑問にも丁寧に対応しながら、土地の売却をサポートいたします。
お客様一人ひとりに寄り添ったサービスを用意しつつ、売却活動や仲介手数料に関する疑問にも丁寧に対応いたしますので、土地の売却を検討中の方はお気軽に三菱地所の住まいリレーにご相談ください。
掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。
三菱地所の住まいリレーでは、他にも住み替えに関するお役立ちコンテンツを豊富に取り揃えております。是非、お気軽にご参照ください。
マンション・土地・一戸建てさっそく無料売却査定を始める
※査定可能エリアのみ表示されます。ご了承ください。
都道府県
市区町村
町名
最適な賃貸プランをご提案しますさっそく無料賃料査定を始める
※査定可能エリアのみ表示されます。ご了承ください。
都道府県
市区町村
町名